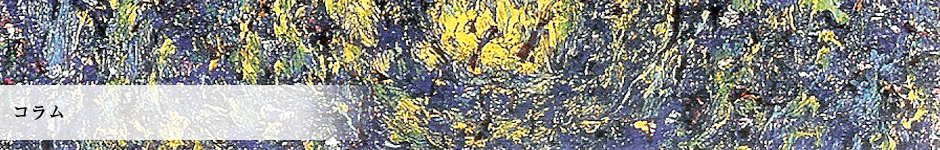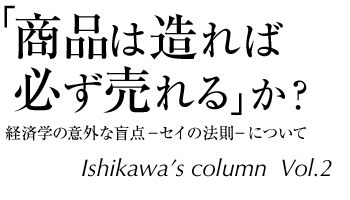
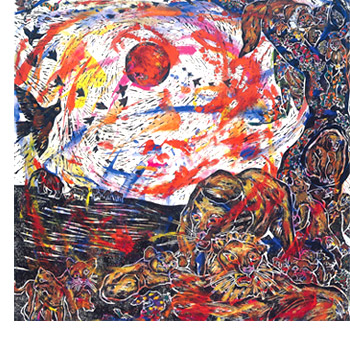
ちょっと昔ではマルクス経済学、近代経済学を対比させた議論、最近では新市場原理などの議論の中で、意外に見落とされているのが「セイの法則」です。
セイの法則、「供給はそれ自身の需要を創造する」と要約される仮説でと定義しましょう。簡単に言うと「商品は造れば必ず売れる」ということです。
これだけを見ると、誰でも「そんなばかな」と思うかもしれません。しかも、故・森島通雄先生は、実際「セイのドグマ」と呼んでおられたし、この法則なるものは、現代では好況等で十分に潜在需要がある場合や、戦争等で市場供給が過小な場合に成り立つ限定的なものと考えられていたはずです。
また一般に多数の耐久財 (Durable good) ・資本財 (Capital good) がある経済社会を想定していないことが(耐久財のディレンマ)ほぼ明らかなのです。
アダム・スミスが「レッセフェールによって理想的な状態になる」と言ったあたりは、このセイの法則が前提にあります。
マルクスが、一部の金満なブルジョアジーの搾取によって、その他多数が労働力しか売るもののないプロレタリアートに分化し、そこから常に「失業」と「貧困」がおこると考え、そしてこの桎梏(しっこく)が革命の到来を必然的なものとすると分析した前提にもこのセイの法則があります。
誤解されている点は、マルクス信者たちが、大恐慌はマルクスが予言した資本主義の矛盾の発現のように言っていた点ですが、これに対して、実際マルクス本人が大恐慌を予測していた形跡はありません。「現存人口にとって過多な生産手段が生産されるのではなく、資本の儲けとの関係で過剰であるにすぎない」というのがマルクスの「恐慌」の結論です。
(需要の欠落これについては、ケインズが、有効需要を創出できることを発見しました。)
マルクスの「革命予言」が当たらなかったのは、西側の体制では、「国民の経済」に歪みや偏りが起こるようであれば、税金や補助金や社会保障給付などによって、所得の再配分を政府が行う、いわゆる「厚生経済学」的な考え方で修正してきたからでしょう。
ところが、1991年のソ連崩壊からインターネットの波及とが重なって情報、金融のグローバル化が起こり、先進資本主義国において、市場をどのようにでもコントロールできると思う過信の元、デリバティブをはじめとした金融先物商品によるマネーゲームが金融機関と投資家たちを躍らせたことは記憶に新しいところです。
市場における「完全競争」という理想的な市場が出現しているとみなしたのが新自由主義経済学で、「完全競争」こそが「自由競争」で、そこではヒト・モノ・カネは必ずやベスト・レスポンスをもって再配分されるはずだから、政府は所得や富のシステムにはできるかぎり関与せずに「小さな政府」であるべきとしました。よく見てみると、この前提にもセイの法則が潜んでいます。
安い金利で資金を何倍にも膨張させることができるとするレバレッジ[てこの理論]も、オランダのチューリップバブルや、平成バブルで使い古されたにもかかわらず、また登場してきました。使っても減らない「円天」などのまがい物はすぐ分かるのですが、金は投資すれば必ず儲かるというセイの法則を前提にしたレバレッジ理論の詐術の術中にはまるのは何故でしょう。
要は、資本主義の富の蓄積は放っておけば、「失業」と「貧困」が生じてしまうこと、商品需要には限界があり、それによって、日本では、「派遣切り」をはじめとする貧富の格差をますます大きく広げつつある社会に移行するおそれがあるということです。