
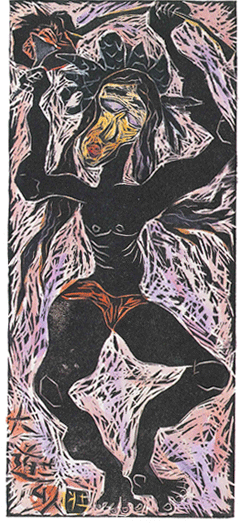
いろいろあった前世紀の嘘の一つに"前衛"という言葉がありました。
それには、マルクスが「革命は必至である」(※前回のコラム参照)と、経済学の分野でしながら政治論として、軍隊的な鉄の規律に依る労働者階級や大衆を指導する前衛党が必要だと説いたことから始まりました。工業後進国であったロシアのレーニンがさらにそれを理論的に深めたというのが、20世紀では"はやり"でありました。
そもそも、王権神授説のような構成でもなく、神に選ばれた預言者でもないのに、何故そのような卓越した能力を持つ政治組織ができるのか不思議ではあったのですが、次第に元祖"前衛"、本家"前衛"のような争いの起きる中で、自らマルクス、レーニンのいう前衛党であると自称する組織がありました。
しかし考えてみると、そのような政治的党組織がどうして存在しうるのか全く不明ではありませんか。
"奇蹟を信じ、預言者の言葉に絶対的に帰依するという、信仰が前提にないとこの"ご指導さまの組織"は成り立たないはずで、つまりは、マルクス、レーニンを預言者として信じなければ、成り立たないものでしょう。
しかもこの宗教を否定する宗教はとんでもない方向に行きました。その根底には、いわゆる憎悪の哲学があったのでしょう。小泉信三氏は、著書「平生のこころがけ」のなかで、「憎嫉(ぞうしつ)は元来人間の恥ずべき弱点である」とし、そのうえで、マルクス主義について「すでに人間にこの性情があるとすれば、この悪念を煽動して、他人の富貴の羨むべく、他人の栄華の憎むべき事を説く学説が、いかに人心に投じ易いかは、想像に難くない。マルクシズムは正にそれであって、マルクシズムの哲学的・社会学的・経済学的根拠に対する論評はどのようにあれ、それが憎嫉の体系化として、思想史上第一のものであることは、争うべくもない」と指摘していました。
そして革命運動における指導政党であるといううぬぼれは、更にその「うぬぼれ」が暴走し、科学的真理の唯一の認識者、体現者であると自負し、前衛党以外の者はその真理を認識できない者とする、暴力的差別イデオロギーになっていったのです。
小泉信三氏が共産主義国について、「そこでは権威に対する極度の畏怖が人心を支配し、何が真理であるか、何が虚偽であるか、何が尊敬さるべきか、何が憎悪もしくは軽蔑されるであるかが、各人の判断に委せられず、一々指図されていることである」と述べた点はこのような差別イデオロギーから当然出現する状況であったわけです。
これが自由主義国では、傲慢なうぬぼれを持ちながら、慈悲深い人格者を装ったり、わかりもしないこと、知りもしないことを、全知全能であるかのように知ったかぶりをしたりするような政治的な手法を繰り返すことになってしまい、ヒンシュクを買うことになるのです。[つづく]








